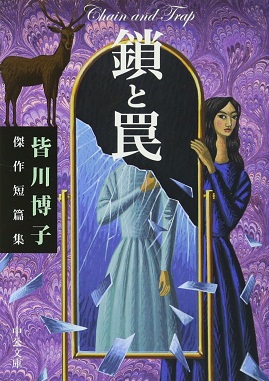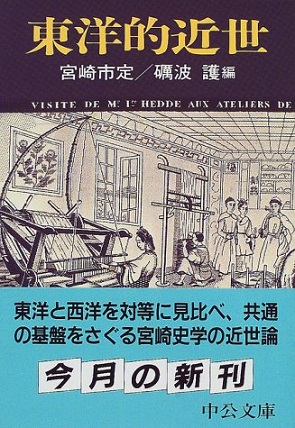��ŕ��ɏ����W��
�������� �y�݁z
�z�[���@�b�@�������ɖڎ�
�O�Y �N�Y�@(�݂���Ă낤)
������̖e��@(��������̂���)
�O�Y ��m�@(�݂���܂���)
���̂̕ϗe �\ ���㕶�w�m�[�g��@(���ソ���̂ւ�悤)
�O�� �R�I�v�@(�݂��܂䂫��)
���Ƙ_��@(���������)
�O�� �R�I�v (�݂��܂䂫��)
����z�ƓS� (�����悤�ƂĂ�)
�Ȓ��n�Ռ���E�O���R�I�v���@(���傭�Ă�����E�݂��܂䂫��)
����|������@(����݂͂�Â�)
�O�� �R�I�v (�݂��܂䂫��)
�ᚉ��̃e���X� (�炢�����̂Ă炷)
���� �ׁ@(�݂����݂Ƃ�)
���x���|������@(�������イ�Ԃ������傤)
���� �ׁ@(�݂����݂Ƃ�)
��F��_��`��q�㉺���r�@(���̂������ł�)
���� �� (�݂����݂Ƃ�)
��n��Ԗ�ɖ���ׂ�� (���܂�͂Ȃ̂ɂ˂ނ�ׂ�)
���� �ׁ@(�݂����݂Ƃ�)
��Ă�������@(�Ă����݂�)
���� ���@(�݂����݂Ƃ�)
��킪�Z���̈Ŗ��@(�킪�낭�ǂ��̂�݂�)
���� �������@(�݂���������)
��s�v�c���s��@(�ӂ�����傱��)
�~�b�L�[ ���� (�݂����[�₷����)
��ӂ��炢�V���w�L �\ 50�N��A�����J�A�j�V�r�Ȑt� (�ӂ��炢�ڂ���イ������)
���� �� (�݂����킵�イ)
��؎����@���{���v���V���ɂ����������j(�㒆��)� (���������イ����)
���c �㔪��Y (�݂������킶�낤)
�����������ǂ� �\ �����W��2176��� (������Ԃ�����)
���c �㔪��Y�@(�݂������킶�낤)
��q���V�}�E�i�K�T�L�ւ̗� �\ �����̔�ƈ�Ղ�����@(�Ђ낵�܂Ȃ������ւ̂���)
�O�J ��n (�݂��ɂ�����)
��]�ˏ��������}�G� (���ǂ���݂�ӂ���������)
�O�J �M (�݂��ɂ܂���)
����F�O���R�I�v� (���イ�䂤�݂��܂䂫��)
�O�c�� ���ҁ@���q ���F�Z���@(�݂��ނ炦��E��������͂�Ђ�)
��]�˔N���s����@(���ǂ˂イ���傤��)
(�摜�̓N���b�N�Ŋg�債�܂�)
��428��
�����s 1981�N
���ژ^��
����V�N���s���������N���s��������߁A��V�g���N���s����ȂǑ�\�I�N���s���\�ܕт����߁A�]�˕����Ɛ������Ԃ𖾂炩�ɂ���B
������ŁE���q���F
�F�� ���q�@(�݂Ȃ���Ђ낱)
��d�������E�l������@(���₩�����炳������)
�F�� ���q (�݂Ȃ���Ђ낱)
�����㩁@�F�씎�q����Z�яW� (������Ƃ��)
�F�� ���q (�݂Ȃ���Ђ낱)
��Ԉţ (�͂Ȃ��)
�{�� �������@(�݂₨������)
����ɏE�����b��@(���тɂЂ�����͂Ȃ�)
�{�� �����@(�݂₨������)
��ٍ��H���|�l�n������@(�������ւ�낽�т����ɂ܂�)
�{�� �ЗY�@(�݂₪��Ƃ炨)
��H䇓��l������@(���イ�����ǂ������Ԃ�)
�{�� �s���@(�݂₴����������)
���i���l�@�̌��� �\ �ȝ��O�j��@(���イ�Ђ�ق��̂��イ)
�{�� �s�蒘�E��g ��� (�݂₴�����������E�ƂȂ݂܂���)
����m�I�ߐ�� (�Ƃ��悤�Ă�����)
�{�� �s�� (�݂₴����������)
���̎��x�� �\ �ܐ��I�̓��A�W�A�Ɠ��{� (�Ȃ��̂������Ƃ�)
�O�D �O (�݂悵�Ƃ���)
������E���c���i� (����������������)
�O�D �O�@(�݂悵�Ƃ���)
��ߑ�W���[�i���X�g��` �\ �V�n�̔@���q�㉺�r��@(��������[�Ȃ肷�Ƃ�ł�)
�O�D �O�@(�݂悵�Ƃ���)
��܂ނ��̎��Z �\ �ݒ��ꣁ@(�܂ނ��̂��イ�낭)














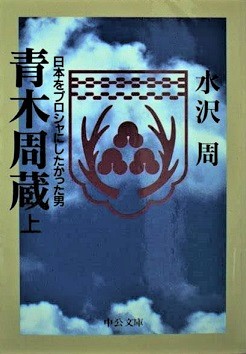



.jpg)