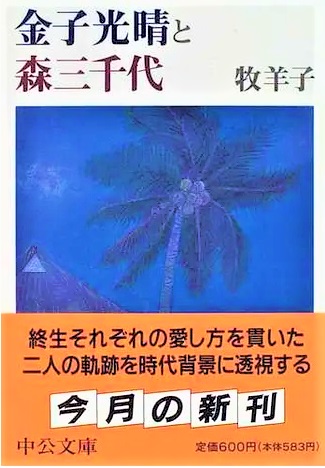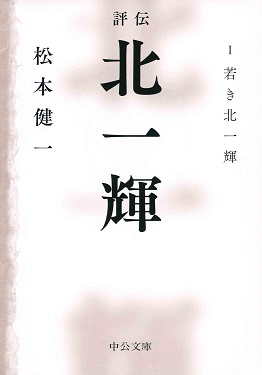��ŕ��ɏ����W��
�������� �y�܁z
�z�[���@�b�@�������ɖڎ�
�O�� �r�V�� (�܂������Ƃ��䂫)
��������L� (���ׂ������カ)
�q �r�q (�܂��悤��)
����q�����ƐX�O��� (���˂��݂͂�Ƃ���݂���)
�q�� ���v�@(�܂��ނ炽����)
��_���R�� �\ �o�ł���Ȃ���@(��������܂�)
�q�� �L���@(�܂��̂̂Ԃ���)
���ژ^� �㉺���@(�������낭)
�}�[�N�E�I�[���� �X�^�C���� ���c ���j�� (Mark Aurel Stein�E�܂��Ђ���)
��R�[�^���̔p�У (���[����̂͂�����)
��������BIBLIO
���@ �����@(�܂��ނ˂͂����傤)
����N�̏H��@(���Ƃ��̂���)
���c �`�Y�@(�܂����悵��)
����z�ƌ��̐_�a �\ �Ñ�A�����J�����̔�����@(�����悤�Ƃ��̂���ł�)
���c �O�Y���@(�܂������Ԃ낤)
����q��@(����)
���� ���� (�܂�����������)
��V�w�T� (�䂤����)
���� �V���@(�܂����Ă�݂�)
������@(����)
�}�b�V���E�O���b�����f�B�@�Đ� �Ǖv�� (��˂����傤��)
����m���X�v�[�`����@(���������炷�Ձ[����)
���c �B���@(�܂�������)
������̃S�A�����L �\ �����̐ړ_��K�˂ģ�@(��������̂�������������)
���c �B���@(�܂�������)
���؏����@(�Ȃ���ꂢ)
���� �L�c�@(�܂Ȃ��䂤����)
����� �\ �C���h������{�ւ̓`����@(�݂����傤)
���� �L�c�@(�܂Ȃ��䂤����)
�����o��@(�肵�カ�傤)
���� ��}�@(�܂炩����)
���A�_���X�z�[���̖��@(������ف[��̂��)
���{ ��j�@(�܂��Ƃ�����)
����w�ǁ@�Y���ꂽ�M���q��@(���傤������傤�E�킷���ꂽ��������)
���{ ���� (�܂��Ƃ���)
��]�` �k��P�@�T �Ⴋ�k��P� (�Ђ傤�ł�������)
���{ ���� (�܂��Ƃ���)
��R�{�o�n�@�t�E�����w�S��V�_�x� (��܂��Ƃ�����)
���{ �����@(�܂��Ƃ������傤)
��\�l���̉R��@(�����イ���܂��̂���)
���{ �����@(�܂��Ƃ������傤)
����_��@(���)
(�摜�̓N���b�N�Ŋg�債�܂�)
��318��
�����s 1984�N
���J�o�[����E����L
���ژ^��
�b�M�̖���ʂ�琢�Ɩ핽���B���S���������Ȃ�ʐ��ɕ�����]�ƈ���`���퍑���}���Ɏ������w�̕��c���L�B��M���R�L��^����B
������ŁE����G��
���R �� (�܂�܂��킨)
��Q�O�@�@�B�̂Ȃ��̓� (���イ)
�}���I�E�o���K�X=�����T�� ���� �p��Y�� (Mario Vargas Llosa�E�ɂ��ނ炦�������낤)
��h���E���S�x���g�̎蒟� (LOS CUADERNOS DE DON RIGOBERTO)
�}�[����������� ���� �Ζ� (�܁[��₾����������E�Ђ炨���݂ǂ�)
��Ō�̃��V�A������@�v�����̃��}�m�t���ƣ (�������̂낵��������������)
�������� BIBLIO20���I