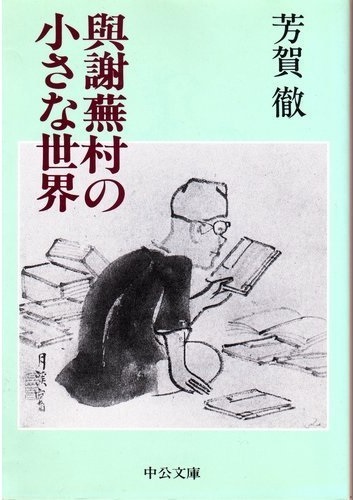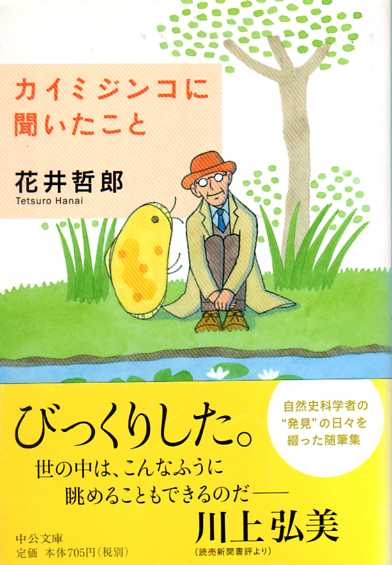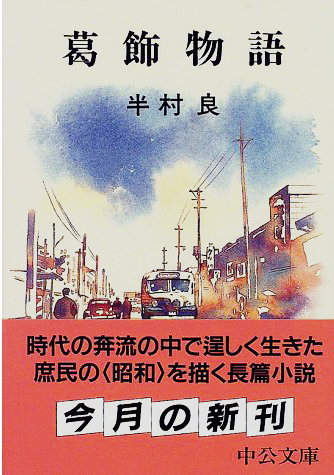絶版文庫書誌集成
中公文庫 【は】
芳賀 徹 (はがとおる)
「與謝蕪村の小さな世界」 (よさのぶそんのちいさなせかい)
萩原 朔太郎 (はぎわらさくたろう)
「帰郷者」 (ききょうしゃ)
萩原 延壽 (はぎののぶとし)
「馬場辰猪」 (ばば たつい)
萩原 葉子 (はぎわらようこ)
「父・萩原朔太郎」 (ちちはぎわらさくたろう)
(画像はクリックで拡大します)
*265頁 / 発行 昭和54年
*カバー・舟越保武
*カバー文
不世出の詩人を父に持つ著者が、詩人の家族、交友、日常を、若き日の記憶の糸をたぐりつつ克明に描き、その全人像を再現した著者の第一作。文庫化にあたり初めて全篇に加筆推敲を加え、初版後に執筆の八篇をも収録した増補完結定本。
萩原 葉子 (はぎわらようこ)
「木馬館」 (もくばかん)
(画像はクリックで拡大します)
*253頁
*発行 1991年
*カバー・萩原朔美
*カバー文
戦中戦後の甚だしい食糧難と貧苦の日々、心通わぬ夫との結婚そして出産、口さがない女たちの欲望むき出しの井戸端会議や醜い争い。でも振り返ってみれば楽しいことばかりだった気がする…。崩れかかった共同住宅「木馬館」に身を寄せあって生きる人々の日常に人生の縮図を映し『蕁麻の家』以後を描いた著者初の長篇。
萩原 葉子 (はぎわらようこ)
「燃えるアダジオ」 (もえるあだじお)
白雲荘主人 (はくうんそうじゅじん)
「張作霖」 (ちょうさくりん)
土師 清二 (はじせいじ)
「砂絵呪縛 前後篇」 (すなえしばり)
橋本 治 (はしもとおさむ)
「江戸にフランス革命を!〈上中下〉」 (えどにふらんすかくめいを)
(画像はクリックで拡大します)
*上185頁・中224頁・下249頁 / 発行 1994年
*下巻カバー絵・豊原国周「伊達競於国戯 御殿床下之場」部分(高橋誠一郎コレクション・慶應義塾図書館蔵)
*カバー文
上 江戸という哲学
歌舞伎、日本髪、着物……江戸という“過去”の持つ呪縛を解き放ち、自由になる為に、現代に生きる我々は再び、それぞれの呪縛を明確にするべきなのだ。“過去”という“美”を手に入れるために。 ―― 橋本治の挑発的文化論。
中 江戸はなぜ難解か
大江戸ローマ帝国説、大奥の論理、イキとヤボ、騎士とサムライ、土地問題の由来、忠義の構造、江戸の会社員は結婚出来なかった、など江戸を解き、江戸と現代を繋げる52の断章。都市生活とは贅沢とはそして“自由”とは。
下 江戸のその後
江戸町人文化が文明開化によって闇の中に消えゆく時期に活動した「最後の浮世絵師」たち。彼らの絵から“江戸”を逆照し、“日本の近代”を問う新視点の明治論。平賀源内唯一の“思想書”である『痿陰隠逸傳』論考も含む完結篇。
*目次
上
呪縛の意匠 ―― 過去へ行く為に
Ⅰ
古典の時代 ―― もう一度、歌う為に
「集団批評の精髄 ―― あるいは全体を語る個について」
愛嬌 ―― または幻想する肉体
怪 ―― 歌舞伎の論理)
Ⅱ
江戸の“様式(てつがく)”
江戸の段取り
江戸の“総論”
中
Ⅲ
江戸はなぜ難解か?
1大江戸ローマ帝国説 2江戸はとっても難解だ 3江戸は色々に江戸である 4江戸は漢字の世界でもある 5江戸はモチロン日本史の中にある 6明治維新はサムライ・クーデター 7江戸は勿論管理社会だ 8大奥の論理 9江戸の治外法権 10江戸は結局キモノの世界だ 11行方不明というヘアスタイルはどうして生まれるか 12江戸の贅沢 13江戸のワンパターン 14江戸のデザイン 15イキとヤボ 16江戸は何故重要か 17江戸とヨーロッパ 18騎士とサムライ 19江戸の開明度 20江戸の教養メディア 21江戸のよく分かんない知性 22江戸の学問 23江戸の実業 24江戸の実業じゃない方 25江戸の近代自我 26江戸のクォリッティライフ 27江戸の文化小革命 28江戸のサブカルチャー 29江戸の町人は余分な存在だ 30土地問題の由来 31都市とその後の親不孝 32農民作家はなぜいない 33農民という不思議 34悪代官と必要とする被害者の論理 35米本位制は過去の日本の一切の根本である 36「百姓に学問はいらない」と言って、日本の農村は近代を拒んだ 37江戸の街は街区(ブロック)じゃない 38江戸に貴族はいない 39江戸は勿論、法人社会だ 40江戸の契約 41江戸の終身雇用 42江戸の見習い社員 43江戸の一人前 44忠義の構造 45武士の根本 46近代がやって来た日、武士は突然消滅する 47江戸の会社員は結婚出来なかった 48“主人”という制度 49家族制度は近代の暗黒面だ 50江戸のシステム 51江戸の“恋愛”は結婚と並行する 52自我というのは贅沢だ
下
Ⅳ
明治の芳年
私の江戸ごっこ
安治と国芳 ―― 最初の詩人と最後の職人
Ⅴ
その後の江戸 ―― または、石川淳のいる制度
彼は一体なにを怒っていたのだろうか? ―― 平賀源内考
立たない源内の『痿陰隠逸傳(ナエマラインイツデン)』、そして国芳の侠気はヤクザの背中に消えて行く
文庫版あとがき
橋本 昌樹 (はしもとまさき)
「田原坂 西南役連作」 (たばるざか)
橋本 昌樹 (はしもとまさき)
「田原坂 増補新版」 (たばるざか)
中公文庫プレミアム 明治の群像シリーズ
蓮實 重彦 山田 宏一 (はすみしげひこ / やまだこういち)
「傷だらけの映画史 ― ウーファからハリウッドまで」 (きずだらけのえいがし)
長谷川 伸 (はせがわしん)
「ある市井の徒 ― 越しかたは悲しくもの記録」 (あるしせいのと)
長谷川 伸 (はせがわしん)
「生きている小説」 (いきているしょうせつ)
長谷川 伸 (はせがわしん)
「印度洋の常陸丸」 (いんどようのひたちまる)
(画像はクリックで拡大します)
*268頁
*発行 昭和55年
*カバー・小林清親「天津城占領之図」(三枚続きその三)明治三十三年八月 井上吉次郎板
*カバー文
第一次大戦下の大正六年、インド洋でドイツ仮装巡洋艦に撃沈された常陸丸の乗船者は、ドイツ本国で転変惨苦の抑留生活を送ることになる。埋れた庶民の心を掘り起す長谷川伸の紙碑『日本捕虜志』の外篇。
*解説頁・村上元三
長谷川 伸 (はせがわしん)
「相楽総三とその同志」上下巻 (さがらそうぞうとそのどうし)
(画像はクリックで拡大します)
*上巻290頁・下巻263頁 / 発行 1981年
*カバー文
上巻
政府の力と光の陰に消えていった相楽総三たちの秘密を掘り起こして照明をあてた雪冤哀史。殉国の人柱にささげる紙の記念碑。
下巻
慶応四年正月、相楽を一番隊隊長とする赤報隊新編成から、信州追分での争闘を経て、罪におとされ刑死するまでを追う雪冤哀史、至情の人柱に捧げる文筆香華の大作。
*解説頁 村上元三
長谷川 伸 (はせがわしん)
「佐幕派史談」 (さばくはしだん)
長谷川 伸 (はせがわしん)
「石瓦混淆」 (せきがこんこう)
長谷川 伸 (はせがわしん)
「日本敵討ち異相」 (にほんかたきうちいそう)
長谷川 伸 (はせがわしん)
「日本捕虜志」上下巻 (にほんほりょし)
長谷川 尭 (はせがわたかし)
「都市廻廊 ― あるいは建築の中世主義」 (としかいろう)
秦 孝治郎・坂本 武人編 (はたこうじろう・さかもとたけひと)
「露店市・縁日市」 (ろてんいち・えんにちいち)
花井 哲郎 (はないてつろう)
「カイミジンコに聞いたこと」 (かいみじんこにきいたこと)
花山 信勝 (はなやましんしょう)
「巣鴨の生と死 ― ある教誨師の記録」 (すがものせいとし あるきょうかいしのきろく)
埴谷 雄高・北 杜夫 (はにやゆたか・きたもりお)
「さびしい文学者の時代 『妄想病』対『躁鬱病』対談」 (さびしいぶんがくしゃのじだい)
埴谷 雄高・北 杜夫 (はにやゆたか・きたもりお)
「難解人間vs躁鬱人間」 (なんかいにんげんvsそううつにんげん)
馬場 恒吾 (ばばつねご)
「自伝点描」 (じでんてんびょう)
((画像はクリックで拡大します)
*253頁
*発行 1989年・2005年改版
*カバー文
リベラルで知られる新聞人が、パリ講和会議、関東大震災、終戦と読売新聞社社長時代など激動の大正・昭和を回想。さらに、お得意の人物評論や随想も収録。
*目次
序 / 自伝 / 人生随想 / 思い出す人々 / 評論 / 馬場さんのこと 雨宮庸蔵
羽生 道英 (はぶみちひで)
「幕末 英傑風雲録」 (ばくまつえいけつふううんろく)
早坂 隆 (はやさかたかし)
「戦時演芸慰問団『わらわし隊』の記録 芸人たちが見た日中戦争」 (せんじえんげいいもんだんわらわしたいのきろく)
林 健太郎 (はやしけんたろう)
「歴史からの警告 ― 戦後五十年の日本と世界」 (れきしからのけいこく)
林 達夫 (はやしたつお)
「共産主義的人間」 (きょうさんしゅぎてきにんげん)
林 達夫 (はやしたつお)
「思想の運命」 (しそうのうんめい)
(画像はクリックで拡大します)
*412頁
*発行 1979年
*カバー文
西洋文化の歴史的研究、さらにその批判的搾取の姿勢からはとばしる、古今東西にわたった文化への明敏な考察と良識のあらわれが、平明かつ深厚な一書を成した。昭和十年代を代表する名著。
林 達夫 (はやしたつお)
「歴史の暮方」 (れきしのくれかた)
林 春隆 (はやしはるたか)
「新撰豆腐百珍」 (しんせんとうふひゃくちん)
(画像はクリックで拡大します)
*259頁
*発行 1982年
*カバー文
日本料理書の古典といわれる『豆腐百珍』を現代に蘇らせて、普茶料理をいとなむわざの真骨頂を記し、文献を博捜する豆腐必読百科。「豆腐百珍」「田楽」「豆腐の今昔」「煤掃いと豆腐」「茶席料理と豆腐」「江戸吉原と豆腐」など。
*解説頁・辻嘉一
林 芙美子 (はやしふみこ)
「戦線」 (せんせん)
中公文庫BIBLIO
林 芙美子著 今川 英子編 (はやしふみこ いまわがひでこ)
「林芙美子 巴里の恋 巴里の小遣ひ帳、一九三二年の日記、夫への手紙」 (はやしふみこぱりのこい)
林 芙美子 (はやしふみこ)
「北岸部隊 伏字復元版」 (ほくがんぶたい)
林屋 辰三郎 (はやしやたつさぶろう)
「町衆 ― 京都における『市民』形成史」 (まちしゅう)
林屋 辰三郎・梅棹 忠夫・多田 道太郎 ・加藤 秀俊
「日本人の知恵」 (にほんじんのちえ)
(画像はクリックで拡大します)
*246頁
*発行 1973年
*目録文
「梅干し」「仲人」「じゃんけん」「番付」「系図」「駅弁」「花見」「お守り」「どうも」など45項目の身近な事物を素材にして展開する秀抜な日本人論。
原 勝郎 (はらかつろう)
「南海一見」 (なんかいいっけん)
原田 勝正 (はらだかつまさ)
「駅の社会史」 (えきのしゃかいし)
春名 徹 (はるなあきら)
「にっぽん音吉漂流記」 (にっぽんおときちひょうりゅうき)
半村 良 (はんむらりょう)
「葛飾物語」 (かつしかものがたり)