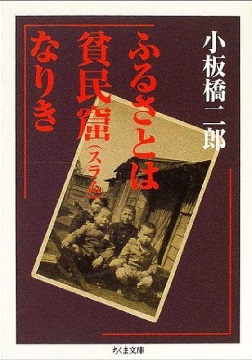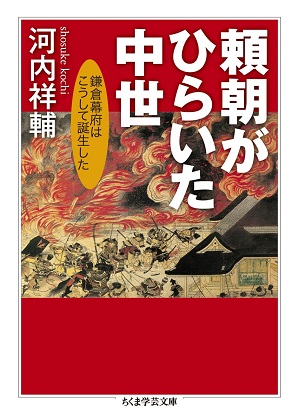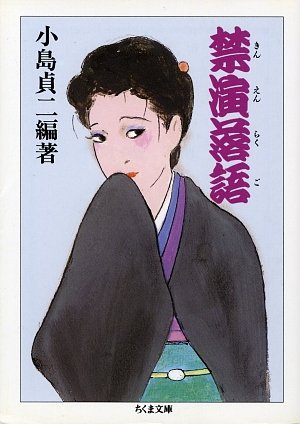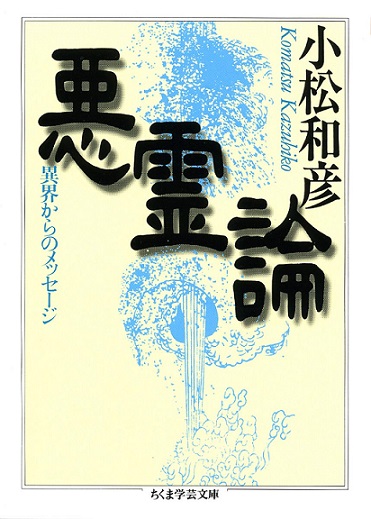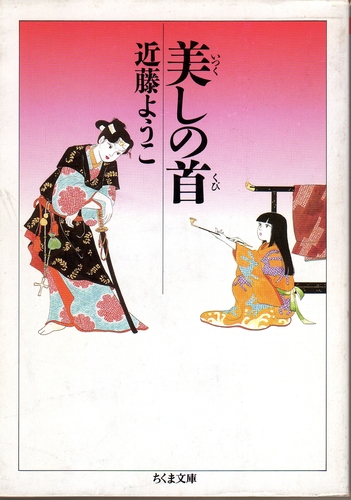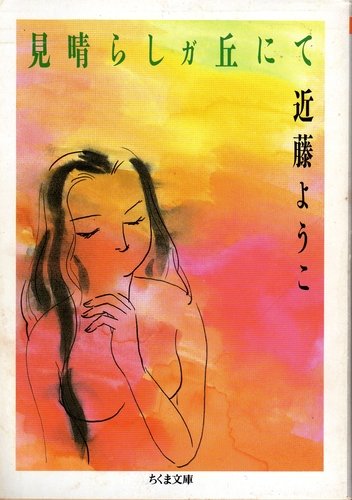*カバーデザイン・神田昇和
カバー図版・三代歌川豊国
「犬塚信乃」「放竜閣之場」
(早稲田大学演劇博物館蔵101-0523)
(画像はクリックで拡大します)
|
*332頁 / 発行 2000年
*カバー文
曲亭馬琴の代表作『南総里見八犬伝』。歌舞伎でもおなじみのこの長い物語は、はたしてたんなる「勧善懲悪の封建的冒険活劇」なのか。かろやかに境界をとびこえて、綺想を広げてみよう。たとえば、ユートピア・安房の「大いなる母」のもとへ集まる犬士たちは、ミシシッピを筏で流れ下るハックルベリー・フィンだ。浜路を拒絶する犬塚信乃は、オフィーリアの死に安堵するハムレットだ。 ―― 「水」や「少年」「竜「」などをキーワードに、トウェインやメルヴィルを重ね、イーグルトン、ユングをひきながら、八犬伝に近代の人間像を読み解く、比較文学からの八犬伝論。新編として、「江戸の二重王権」「『八犬伝』の海防思想」の二論文を増補。
*目次
Ⅰ 八犬伝綺想
序言
第一章 竜の宮媛
第二章 玉なすごとき玉梓
第三章 こよなき仇 ―― 破滅と旅発ち
第四章 永遠の少年たち
(一) 犬塚信乃 / (二) 艶麗なるオフィーリア
第五章 坂東のラヴレイス ―― 網千左母二郎
第六章 再生する女たち
第七章 流離する妖婦 ―― 船虫
第八章 川と少年の物語
(一) 逃走する孤舟 / (二) トム・ソーヤー降臨
第九章 白の系譜学 ―― メルヴィル
第十章 消滅する竜たち ―― 「第九輯」
第十一章 母胎への逃走
(一) 渡河と竜児神 / (二) 祝祭としての戦争
第十二章 父の帰還
(一) 、大法師 / (二) 奔馬のごとく
Ⅱ 江戸の二重王権 ―― 『南総里見八犬伝』再考
はじめに
一 神余・金碗氏の意味するもの
二 外来王と流され王
三 母の身体と父の排除
Ⅲ 『八犬伝』の海防思想
一 (1)『水滸伝』 / (2)外敵 / (3)安房=日本の「置き換え」
二 (1)「操練」の思想と国民皆兵 / (2)水戦・陸戦
むすび
注 / 参考文献 / 文庫版あとがき
解説 八犬伝を構造主義から読む (森毅)
|