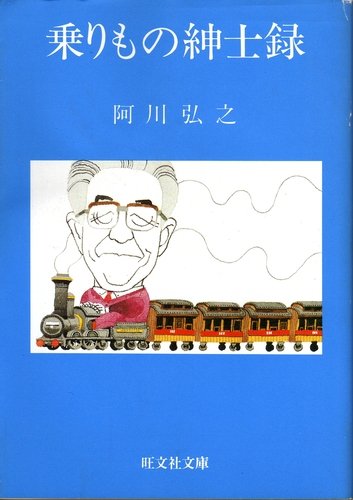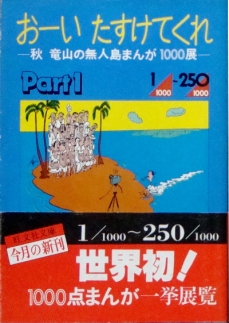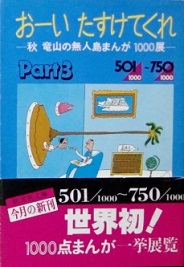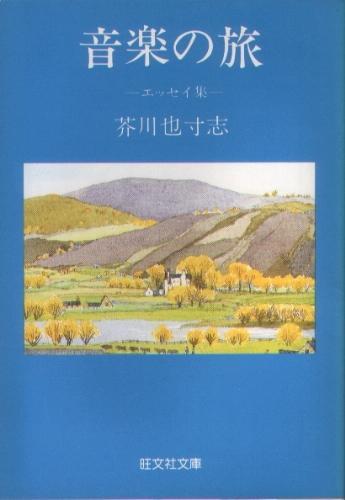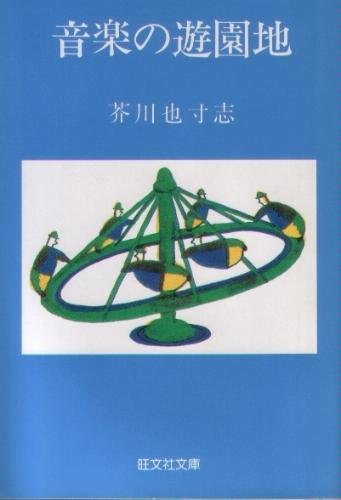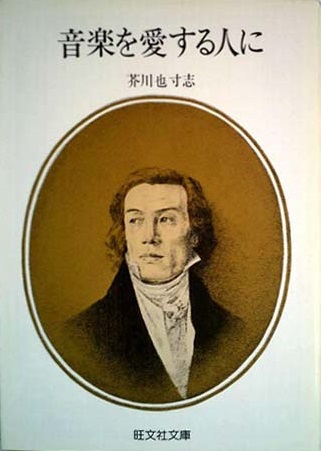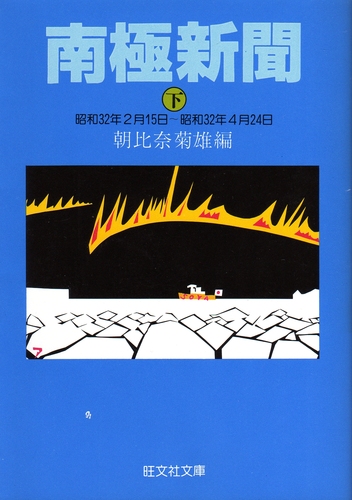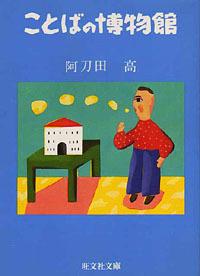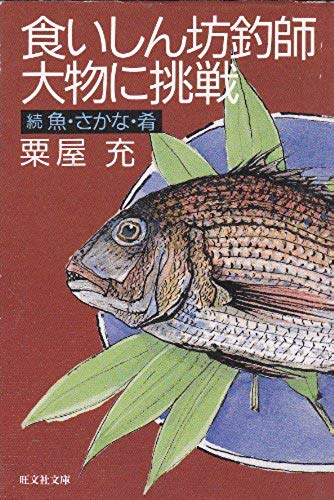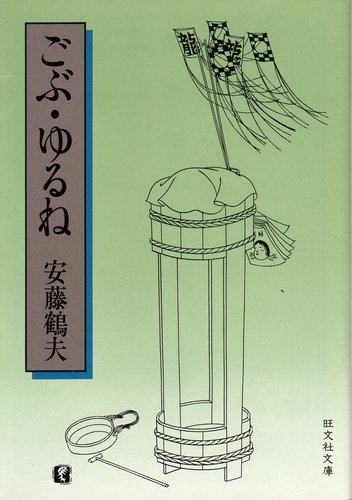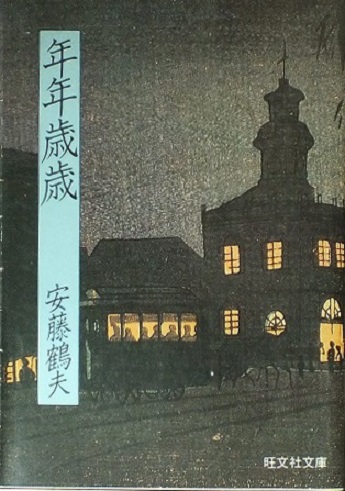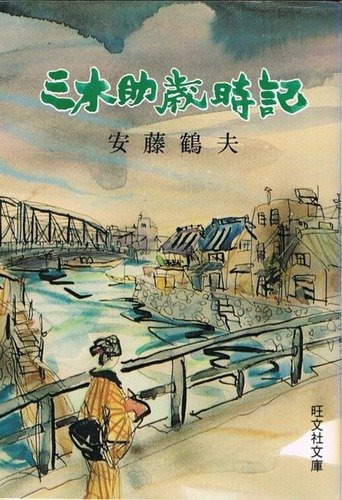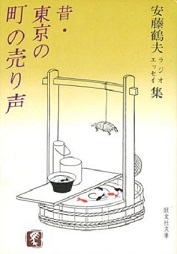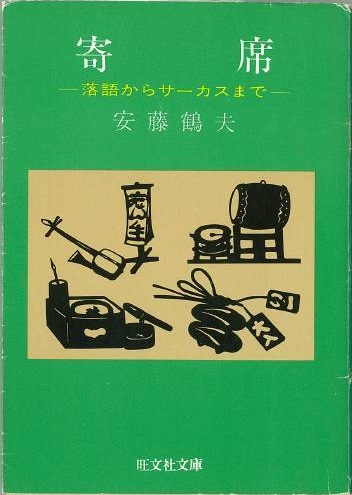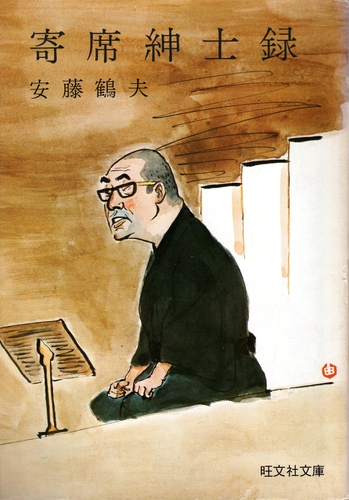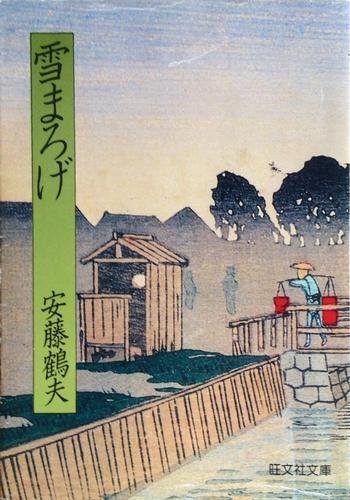絶版文庫書誌集成
旺文社文庫・日本の著作 【あ】
阿川 弘之 (あがわひろゆき)
「乗りもの紳士録」 (のりものしんしろく)
秋 竜山 (あきりゅうざん)
「おーい たすけてくれ 秋竜山の無人島まんが1000展」(全4冊)
(画像拡大不可)
*part1・235頁 / part2・?頁 / part3・234頁 / part4・237頁
*発行 1981年
*目録文
無人島をテーマに、ひとコマ漫画堂々一〇〇〇点の紙上展覧会。楽しいエッセイつきの竜山の世界。
芥川 也寸志 (あくたがわやすし)
「音楽の旅 ― エッセイ集」 (おんがくのたび)
画像はクリックで拡大します
*213頁 / 発行 1981年
*カバー画・安野光雅
*カバー文
父・龍之介の書斎でストラビンスキーに聞き入った幼少のころの思い出から、現在の作曲家・指揮者の生活までを語る自伝抄「歌の旅」、ひとびとの出会いや外国旅行記を含む「出会ったこと忘れ得ぬこと」、音楽教育への直言「私の音楽教育論」などを収録。すべての音楽愛好家に贈る芥川也寸志音楽エッセイ集。
芥川 也寸志 (あくたがわやすし)
「音楽の遊園地」 (おんがくのゆうえんち)
(画像はクリックで拡大します)
*196頁
*発行 1982年
*カバーとさし絵 長新太
*カバー文
作曲家・指揮者として多年にわたる音楽生活のなかから生れた軽妙洒脱な芥川也寸志ソフト・エッセイ集。「女性にはなぜ大音楽家が生まれないのか」「フルート吹きは白髪型で、オーボエ吹きはハゲが多い」「創作欲と食欲・性欲の関係は」など、音楽好きな人でなくても、ついつり込まれて読んでしまう話49編――
芥川 也寸志 (あくたがわやすし)
「音楽を愛する人に」 (おんがくをあいするひとに)
朝比奈 菊雄編 (あさひなきくお)
「南極新聞」(上中下) (なんきょくしんぶん)
上 昭和31年11月8日〜昭和31年12月24日
中 昭和31年12月29日〜昭和32年2月11日
下 昭和32年2月15日〜昭和32年4月24日
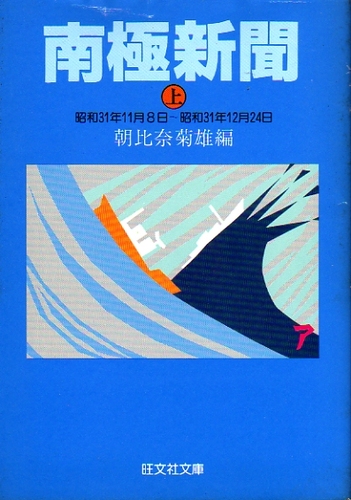
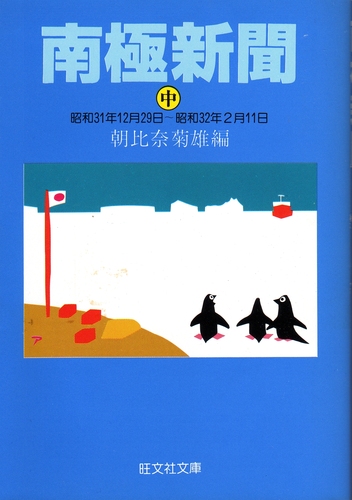
*カバー切り絵・朝比奈菊雄 (画像はクリックで拡大します)
*上・319頁 / 中・316頁 / 下・305頁 / 発行 1982年
*紹介文
・戦後初の国家的プロジェクトである第一次南極地域観測隊の活動全記録。南極観測二十五周年記念出版。
・「南極新聞」とは、昭和31年11月から32年4月までの間、第一次南極地域観測隊を運んだ観測船「宗谷」船内で発行された、雑用紙に謄写版刷りの新聞である。
阿刀田 高 (あとうだたかし)
「ことばの博物館」 (ことばのはくぶつかん)
(この画像はクリックしても拡大しません)
*222頁 / 発行 1984年
*目録文
「酒池肉林」「雪隠」から「フレンチ・レター」「ポン・パドゥール方式」まで、天衣無縫の語源談義。
*目次
1章 カンガルーは嘘つき
2章 のぞき屋トムの刑罰
3章 妖姫ポンパドゥール
4章 男は恋で死なない
5章 国士無双は豪傑だ
6章 正直者は馬鹿を見ない
雨宮 和子 / 大井 恭子 (あまみやかずこ / おおいきょうこ)
「アメリカを暮らす」 (あめりかをくらす)
(この画像はクリックしても拡大しません)
*324頁
*発行 1986年
*目録文
カリフォルニアとニューヨーク郊外で長年暮らした二人の著者による゛住んで見たアメリカ"。
有馬 頼義 (ありまよりちか)
「三十六人の乗客」 (さんじゅうろくにんのじょうきゃく)
*280頁 / 発行 1976年
*目録文
三十六人の乗客をのせたスキーバスの中に逃走中の銀行強盗がいる。それを追う刑事。犯人は誰か。 ─ 傑作短篇推理小説集
有馬 頼義 (ありまよりちか)
「背後の人」 (はいごのひと)
*発行 昭和51年
*目録文
恋人の背後に暗い影を見た志戸芳雄は、そこに隠されたものを突きとめようとする。愛と戦争の悲劇を描くサスペンス巨編。
粟屋 充 (あわやしげる)
「魚・さかな・肴 ─ 食いしん坊釣師の料理ノート」 (さかなさかなさかな)
*243頁 / 発行 1985年
*目録文
釣りの楽しさから釣った魚の料理法までを、著者自ら描いた絵を添えて綴った゛おいしく読む本"
粟屋 充 (あわやしげる)
「食いしん坊釣師大物に挑戦 ― 続 魚・さかな・肴」 (くいしんぼうつりしおおものにちょうせん)
安西 篤子 (あんざいあつこ)
「女人紋様」 (にょにんもんよう)
*285頁 / 発行1842年
*目録文
常盤御前・北条政子・淀殿・和宮など、日本史を彩った女性たちの哀しくも美しい生き方を描く。
安藤 鶴夫 (あんどうつるお)
「ごぶ・ゆるね」
安藤 鶴夫 (あんどうつるお)
「年年歳歳」 (ねんねんさいさい)
(画像はクリックで拡大します)
*286頁
*発行 1978年
*カバー文
「年年歳歳」 ─ 既刊「雪まろげ」と併せて、足かけ七年にわたる連載名随筆「食べもののでてくる話」全篇の完結であります。もうひとつ、これも楽しい食べもの屋めぐりエッセイ「あじわう」。味を語りながら、安藤さんはここでも、いつの間にか味の作り手である人びとの、人情の優しさ清しさを語ってしまうのです。
安藤 鶴夫 (あんどうつるお)
「三木助歳時記」 (みきすけさいじき)
(画像はクリックで拡大します)
*561頁
*発行 1975年
*カバー文
冴えた話芸で古典落語にすぐれた芸境をひらいた噺家、桂三木助の一代記。博打三昧に明けくれする青春であり、ドサ回りの苦渋も舐めつくし、踊りの師匠となり、有為転変の末に三代目三木助の名を輝かしいものにした一人の芸人の数奇な人生を描く。その突然の死が惜しまれた安藤鶴夫の絶筆。
安藤 鶴夫 (あんどうつるお)
「昔・東京の町の売り声 ― ラジオエッセイ集」 (むかしとうきょうのまちのうりごえ)
(画像拡大不可)
*274頁
*発行1978年
*カバー絵・三谷一馬
*カバー文
安藤さんはひとも知る語りの名手でした。父親・都太夫の相三味線で鍛えた義太夫声は玄人はだし。落語の゛寝床"ではないが、とうとう商売人の声優さんにまかせておけなくなって、作者自らマイクに向い語り下ろしたのが、名番組とたたえられたニッポン放送の〈ラジオエッセイ〉なのです。本書は、残された台本と放送テープに綿密な校訂を加えて成った初めての集成。決定版であります。
安藤 鶴夫 (あんどうつるお)
「寄席 落語からサーカスまで」 (よせ)
安藤 鶴夫 (あんどうつるお)
「寄席紳士録」 (よせしんしろく)
安藤 鶴夫 (あんどうつるお)
「雪まろげ」 (ゆきまろげ)
(画像はクリックで拡大します)
*213頁 / 発行1977年
*カバー文
むかし「あまカラ」という、ちょいと素敵な雑誌がございまして、安藤さんの名随筆「食べもののでてくる話」が、つねにその誌面を飾っていたのをご存知ですか。のち、その前半を一本にまとめて「雪まろげ」。――絶妙の語り口が冴えに冴える、名著待望の復刊であります。
*解説頁・野口達二
安藤 鶴夫 (あんどうつるお)
「落語鑑賞」(上下) (らくごかんしょう)
*発行1976年
*目録文
文楽・円生・三木助・小さん・可楽等、名人芸として評価高い古典落語を収めた聞書集。「酢豆腐」「芝浜」等二十二題。
*解説頁・江國滋