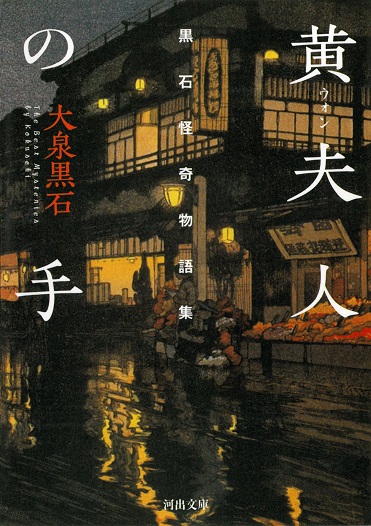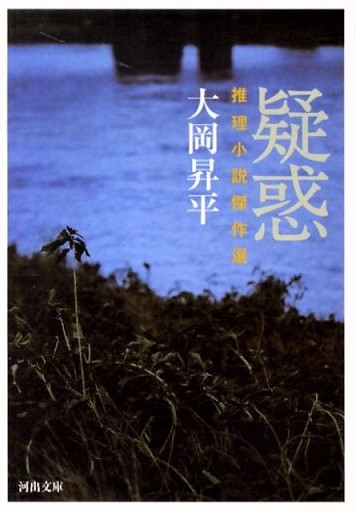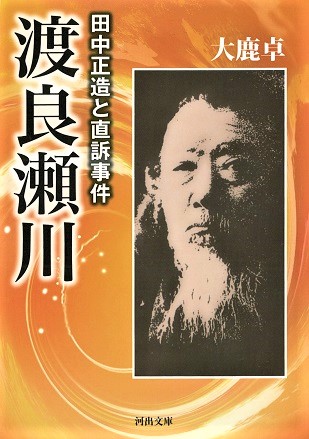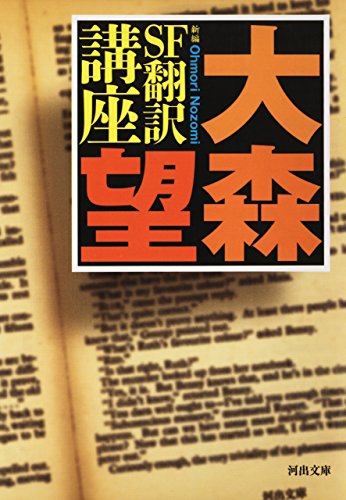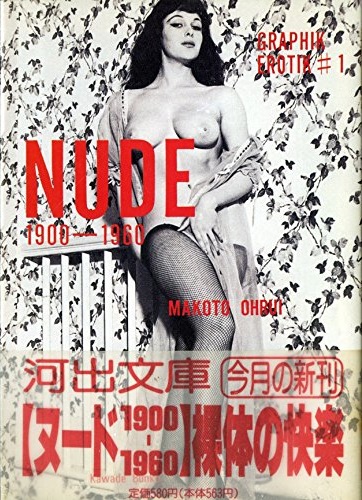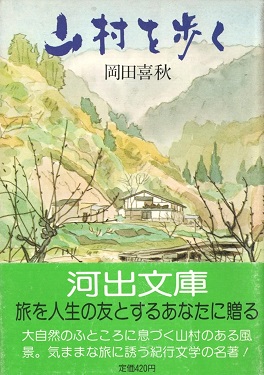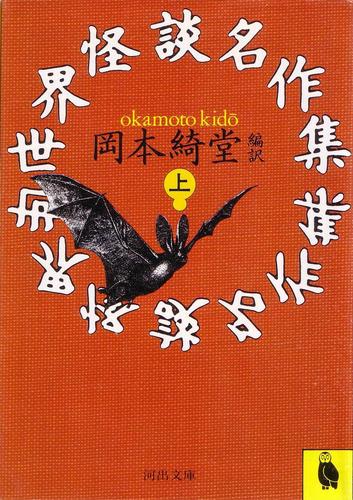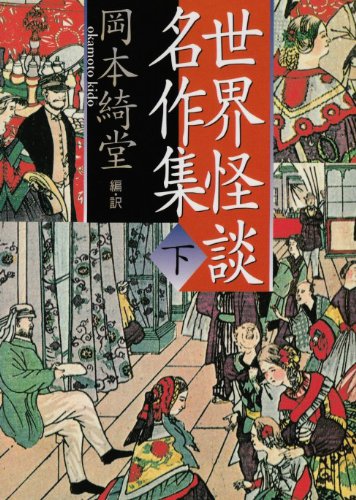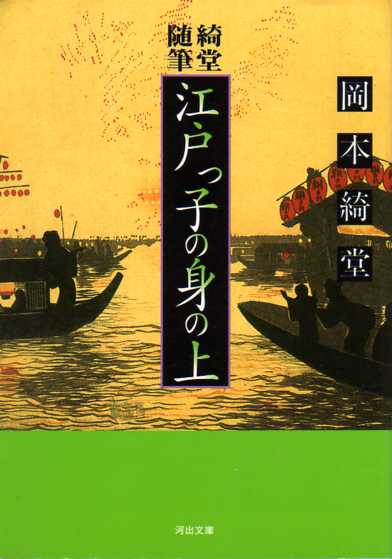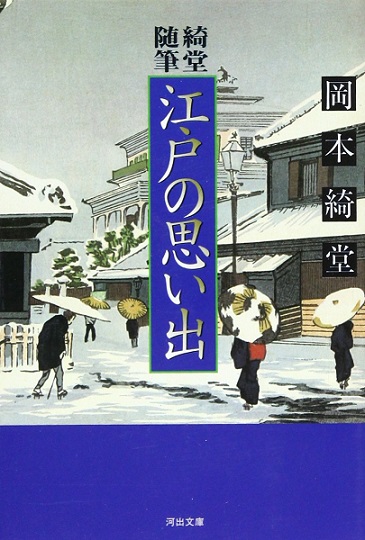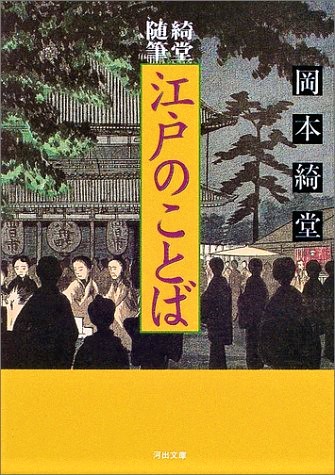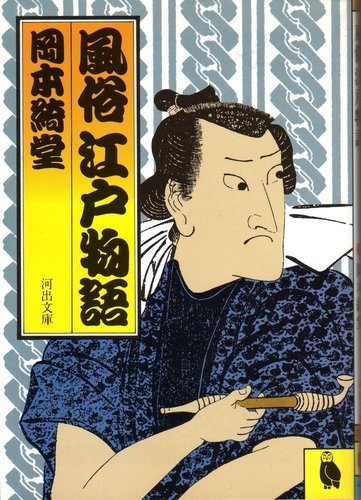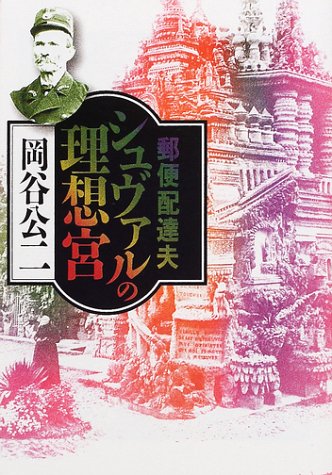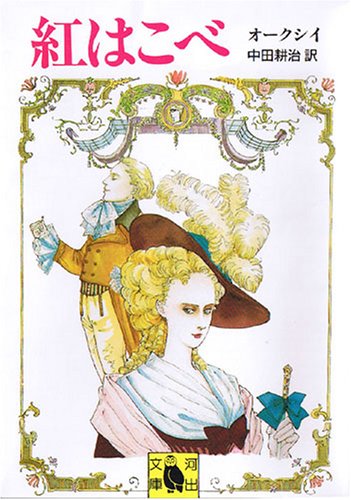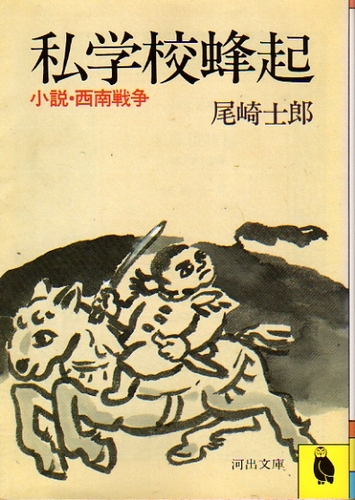��ŕ��ɏ����W��
�͏o���� �y���z
��� ���� (���������݂�������)
����v�l�̎�@���Ή����W� (�E�H���ӂ���̂�)
�剪 ���� (�����������傤�ւ�)
��^�f�@������������I� (���킭)
�厭 �� (������������)
��n�ǐ���@�c�������ƒ��i����� (�킽�点����)
��� �݂Ȏq�@(�����݂Ȃ�)
���a���a��@(���������Ȃ�)
���_ �O�� (�����͂܂Ă�)
������̕�W �\ �����݂̂������E���I�푈� (�߂����̂ڂЂ傤)
��X �] (��������̂���)
��V�� SF�|��u��� (��������ӂق�₭������)
��� �M�� (�����邢�܂���)
��k�[�h 1900�]1960�
(�摜�̓N���b�N�Ŋg�債�܂�)
���Ő�(�m���u��)�����E�J�o�[�������E�ڎ�����
�����s 1993�N
��cover design�FMAKOTO OORUI / cover format�FKIYOSHI AWAZU
���c ��H (�����������イ)
��R�������� (��������邭)
���{ �Y���|���@(�������Ƃ��ǂ�)
����E���k����W ���@(��������������߂��������イ)
���{ �Y���ҁE�� (�������Ƃ��ǂ�)
����E���k����W ��� (��������������߂��������イ)
���{ �Y�� (�������Ƃ��ǂ�)
��Y�����M �]�˂��q�̐g�̏� (���ǂ������Ђ��ǂ����݂̂̂���)
��������(�{�����^)
�@���̏t�̓C���t���G���U�����s�����B
�@���{�ŏ��߂č��̕a�����͂��o�����͖̂�����\�O�N�̓~�ŁA��\�l�N�̏t�Ɏ����Ă܂��܂�����(���傤����)�ɂȂ����B��X�͂��̎����߂ăC���t���G���U�Ƃ����a����m���āA����͕�����(�t�����X)�̑D���牡�l�ɗA�����ꂽ���̂��Ɖ]���\�����B���������̓����̓C���t���G���U�ƌĂ��ɕ��ʂ͂�����(���߂���)�Ɖ]���Ă����B���̂����Ƃ������炵��������(����)�点�����ƑF�c(����)����ƁA�]�ˎ���ɂ������ɔ\(��)���������`�����ɗ��s���āA���̎��ɒN���������Ƃ�������t���Ă��܂����B���x�̗��s�����`�����ꂩ�牏�������Ă����ƌĂԂ悤�ɂȂ����̂��낤�ƁA��(����)�V�l���������Č��ꂽ�B
�@�����ŁA�����Ƃ�������^�����̂̐l�̗���(��傤����)�́A�����炭�����Ɖ]���悤�ȈӖ��ŁA�������v��(�Ђ��܂�)�ɍ��ꂽ�悤�ɁA��(��)���Ɋ�������Ƃ�����ł���炵���v��ꂽ�B����Ȃ�����Ɍ���Ȃ��B����(�Ȃ�)�ł����r(�����)�ł����t(���͂�)�ł��~��(���߂���)�ł���(��)����ł��邪�A�����Ƃ���������ԉ�(�����)�炵���S�P�C(���ǂ�)�Ȃ�������B�җ�ȗ��s���������ĉ��X�ɐl���(����)���悤�ȍ��̕|��ׂ��a���ɑ��āA���ɂ����Ƃ����ł����炵������^�����̂͐�(������)�邨�����낢�ΏƂł���A����(������)�ɍ]�ˎ�(���ǂ���)�炵����������B�������A��̑��h(�����R����)�����s�������ɂ́A�]�ˎ�������ɂ�焈�(�ւ�����)�����ƌ����āA���t�Ƃ��~��Ƃ����t�e�ɂȂ�҂��Ȃ������炵���B�����Ǝ��ʂ���R�������Ȃǂƒq�d�̂Ȃ�����t���Ă��܂����B
�@���ɂ��̕a���������Ɩ����ȏ�́A����ɜߒ�(�Ƃ��)����銳�҂͋v���łȂ���Ȃ�Ȃ��B�����ŁA������菓�(����ɂイ)��h���ɂ͢�v�����磂Ƃ����\�D�����邪��(��)���Ɖ]�����ƂɂȂ����B�V���ɂ�����Ȃ��Ƃ��������B�ܘ_(�������)�A�V���ł͂�������サ����ł͂Ȃ��A�P�Ɉ��̋L���Ƃ��āA��������Ȃ��Ƃ����s����ƕ����̂ł��邪�A���ꂪ��(���悢)���ʂ̖��M���(����)���āA������\�O�A�l�N���̓����ɂ͢�v�����磂Ə��������D�����ɓ\�t���邱�Ƃ����s�����B���ɂ͘I���ɢ������ƣ�Ə������̂��������B
�@��\�l�N�̓A���͏f���ƈꏏ�Ɍ���(�ނ�������)�̔~���~�֍s�����B���̖����g�����ł������B�O��(�݂߂���)�̒牺(�ǂĂ���)������Ă���ƁA�ꌬ�̔_�Ƃ̑O�ɏ\���A���̎Ⴂ����������@(�Ăʂ���)�����Ԃ��āA������������̢�v���邷��Ƃ����������̎��D�����ɓ\���Ă���̂������B���̖T(����)�ɂ͔����~���炢�Ă����B���̕���(�ӂ���)�͍�����Ɏc���Ă���B
�@���̌�ɂ��C���t���G���U�͊��x(��������)�����s���J�Ԃ������A�������̖��͑������Ő₦�Ă��܂����B�n�C�J���̋v���ɜߒ�(�Ƃ��)���ɂ́A��͂�Љ����̃C���t���G���U�̕����������炵���ƁA���̕��͏��Ă����B�������āA���̕��������O�\�ܔN�ɂ�͂�C���t���G���U�Ŏ��B
�����E�v��
��ڗ��C�̕���ɓo�ꂷ��l���B1710�N���̖����̖����������t�̋v���ƐS�����������́C�̍Օ�(������������)�ɂ������ĕ]���ƂȂ�C��ڗ��s�����v���Ԃ̔����ڂ�t�ɂ����Ă��̒�^���m�������B�ߏ�����́s�V�ʼn̍Օ��t�C���ꏕ�́s���͗l���w�叼(���߂��悤�������̂��ǂ܂�)�t�C�߉���k�́s�����v���F�ǔ�(�����Ȃ̂�݂���)�t�Ȃǂ��L���B(�f�W�^���� ���{�l���厫�T+Plus���)
���{ �Y�� (�������Ƃ��ǂ�)
��Y�����M �]�˂̎v���o� (���ǂ������Ђ��ǂ̂�������)
���{ �Y�� (�������Ƃ��ǂ�)
��Y�����M�@�]�˂̂��ƂΣ (���ǂ������Ђ@���ǂ̂��Ƃ�)
���{ �Y���@(�������Ƃ��ǂ�)
������]�˕����@(�ӂ��������ǂ��̂�����)
���J ���� (�����₱����)
��X�֔z�B�v�V�����@���̗��z�{� (�䂤�т�͂����ӂ��ピ����̂肻�����イ)
���� ���v (�����킭�ɂ�)
������Ȕ�� (���������Ȃ���)
���Y �a�� (�������炩���Ă�)
����|�l�̂������i�@���E���Q�E�n��� (���т����ɂ�̂����ӂ�����)
�I�[�N�V�C���@���c �k����
��g�͂��ף�@(�ׂɂ͂���)
���� �m�Y (���������낤)
����Z�ف@�告�o�͎m�A�y�U�̓��O� (����������)
���� �m�Y�@(���������낤)
����w�Z�I�N �\ �����E����푈��@(�����������ق���)
���� ���o�Y (�����ׂЂł�)
��n�[�h�{�C���h�u�� (�́[�ǂڂ���ǂ�����)
���� �M�j (������̂Ԃ�)
��ƍߐ�ȣ (�͂�����)