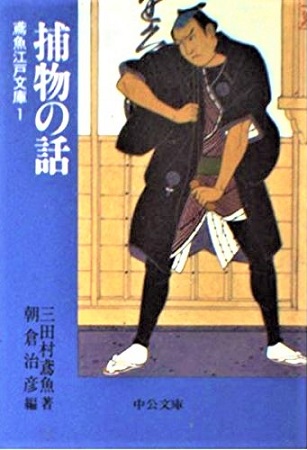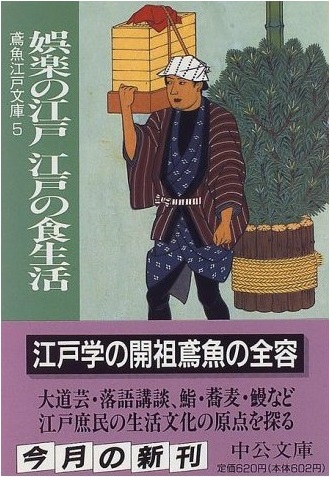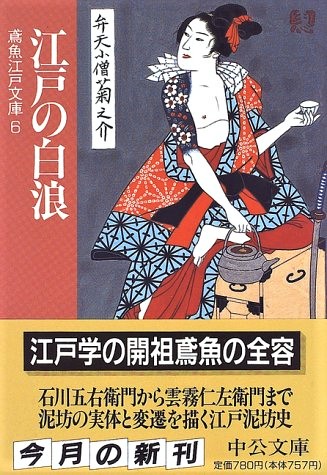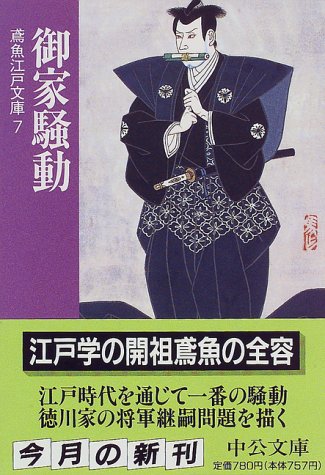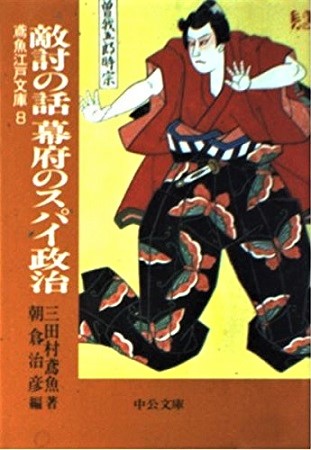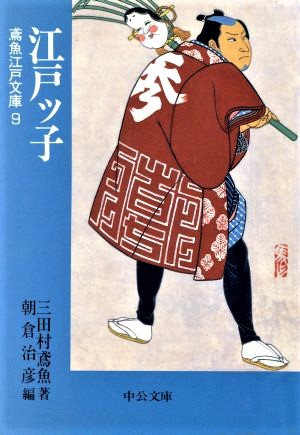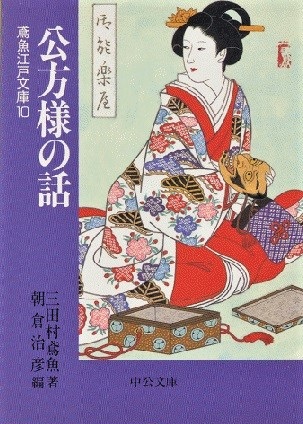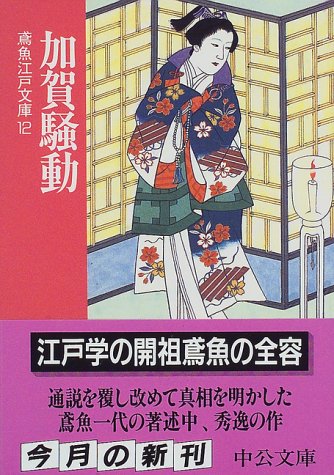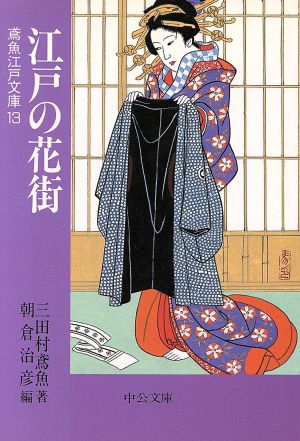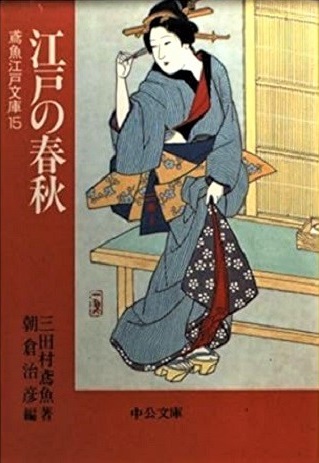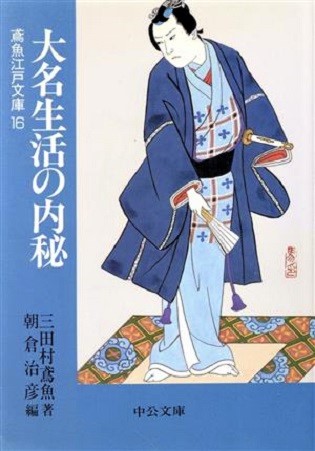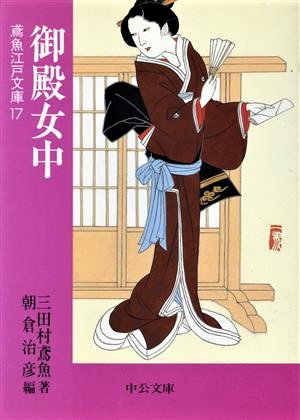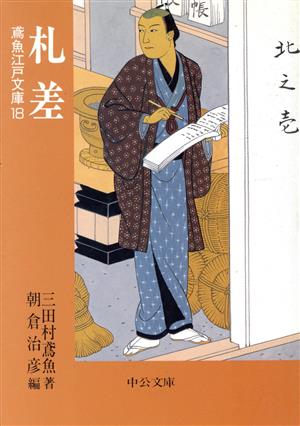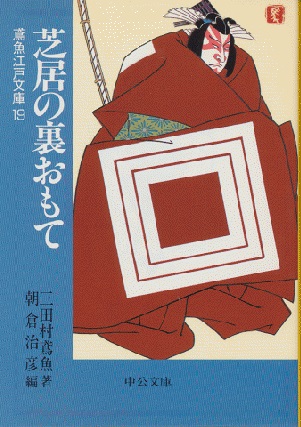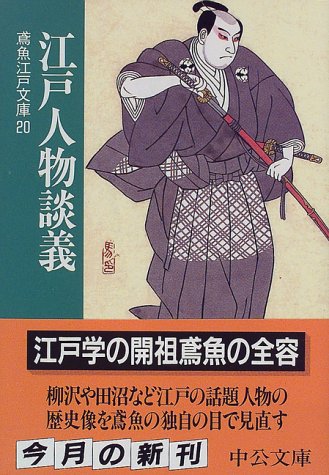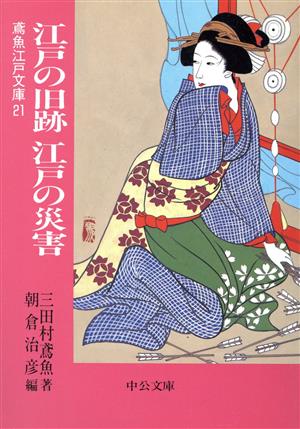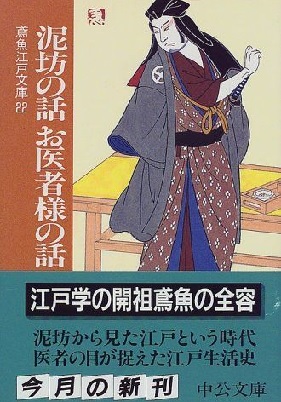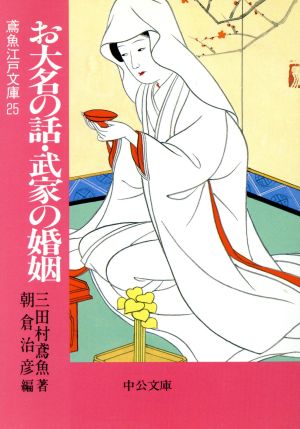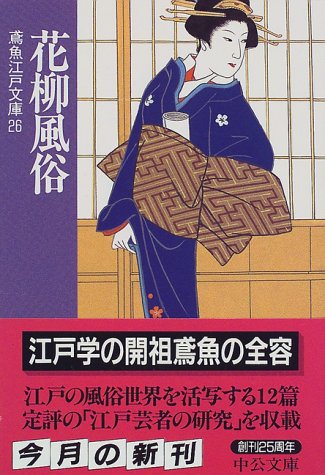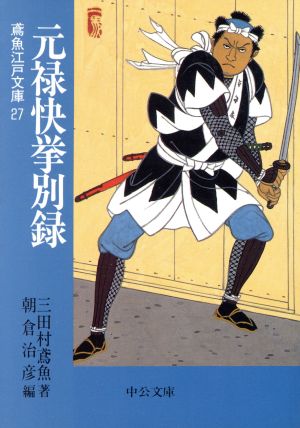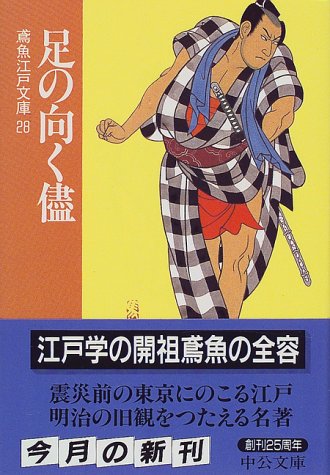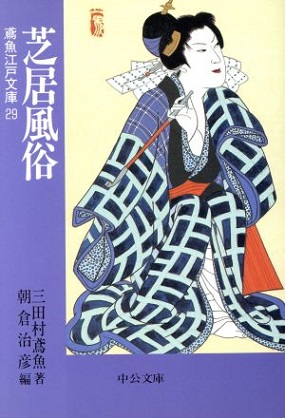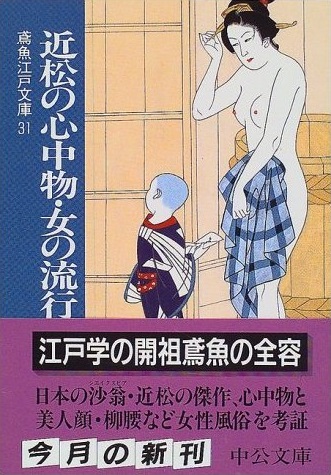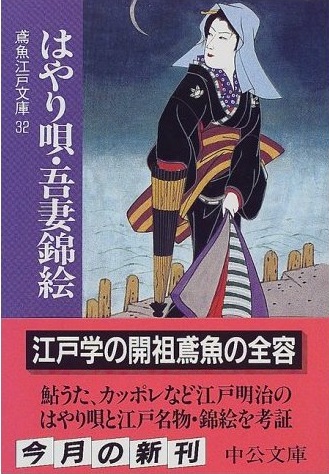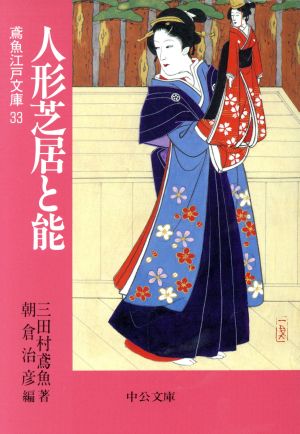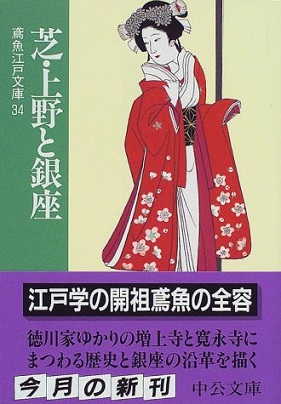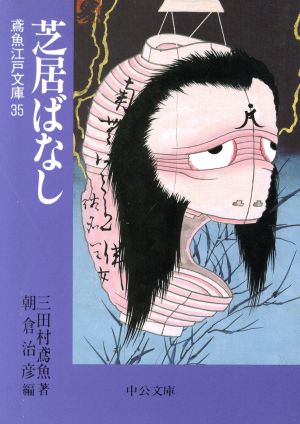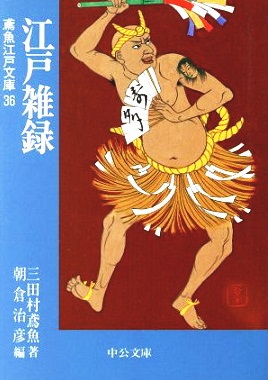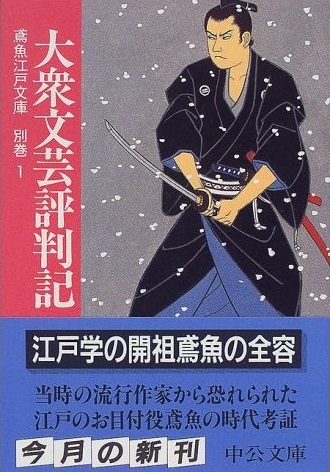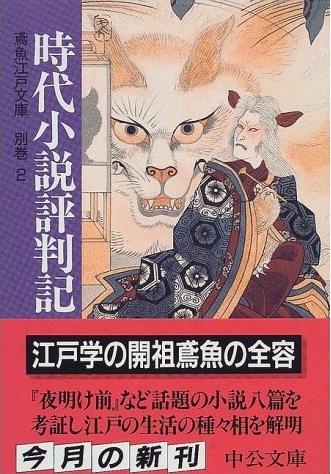絶版文庫書誌集成
中公文庫 【鳶魚江戸文庫 全36巻 別巻2巻】
*全巻カバー画・三谷一馬
〈1〉「捕物の話」 (とりもののはなし)
(画像はクリックで拡大します)
*420頁
*発行 1996年
*目録文
与力・同心・岡ッ引等の捕物の関係者や火付盗賊改・八州取締出役など。江戸の捕物の実際を克明に考証し、以後の捕物研究の嚆矢となった書。〈解説〉山本博文
〈2〉江戸の女 (えどのおんな)
〈3〉横から見た赤穂義士 (よこからみたあこうぎし)
〈4〉「相撲の話」 (すもうのはなし)
〈5〉「娯楽の江戸 江戸の食生活」 (ごらくのえど えどのしょくせいかつ)
(6)「江戸の白波」 (えどのしらなみ)
(画像はクリックで拡大します)
*411頁
*発行 1997年
*目録文
石川五右衛門から雲霧仁左衛門まで、江戸の世を騒がせた泥坊達の人物像とその時代背景・庶民生活を描く興趣尽きない江戸泥坊史。〈解説〉山本博文
〈7〉「御家騒動」 (おいえそうどう)
〈8〉敵討の話 幕府のスパイ政治 (あだうちのはなし ばくまつのすぱいせいじ)
〈9〉江戸ッ子 (えどっこ)
(画像はクリックで拡大します)
*419頁
*発行 1997年
*目録文
開幕後文化の中心地となっていく江戸の姿を歴史的に考究し、江戸の生活文化の変遷を多角的に捉え、江戸ッ子誕生の歴史的背景と特性を明かす。〈解説 山本博文〉
〈10〉公方様の話 (くぼうさまのはなし)
〈11〉武家の生活 (ぶけのせいかつ)
〈12〉加賀騒動 (かがそうどう)
(画像はクリックで拡大します)
*507頁 / 発行 1997年
*カバー文
綿密な実地踏査と適確な資料分析に基づいて、加賀騒動の実相を多角的にとらえ、はじめてその真相を明らかにする。黒田・伊達と共に三大御家騒動の一つとして、小説や講談で名高い加賀騒動の、これまでの通説を覆した、鳶魚一代の著述中、秀逸の作。
*解説頁・山本博文
〈13〉江戸の花街 (えどのはなまち)
(画像はクリックで拡大します)
*321頁
*発行 1997年
*目録文
武士・商人・札差など遊ぶ側の変遷や制度上から考証した「元吉原の話」など、吉原遊廓の発生と遊女の生態を論じた吉原研究六篇。〈解説 山本博文〉
*目次
元吉原の話 / 江戸における第一回の私娼狩 / 江戸の暗娼政策 / 暗娼対治の経験 / 江戸時代の高級遊女 / 奴遊女九重
〈14〉 目明しと囚人・浪人と侠客の話 (めあかしとしゅうじん・ろうにんときょくかくのはなし)
〈15〉江戸の春秋 (えどのしゅんじゅう)
(画像はクリックで拡大します)
*322頁
*発行 1997年
*目録文
江戸の正月、両国の川開き、御殿女中の八朔、天下祭、師走など、年中行事に残る江戸の俤を伝える。江戸の風物と情緒横溢の一巻。〈解説 山本博文〉
〈16〉大名生活の内秘 (だいみょうせいかつのないひ)
〈17〉御殿女中 (ごてんじょちゅう)
〈18〉札差 (ふださし)
〈19〉芝居の裏おもて (しばいのうらおもて)
〈20〉江戸人物談義 (えどじんぶつだんぎ)
(画像はクリックで拡大します)
*398頁発行 1998年
*カバー文
側用人として評判の悪い柳沢の再評価を試みた「正直な柳沢吉保」、大石や堀部の娘たちの真偽を考証した「赤穂義士の娘」、賄賂政治家田沼意次を家臣と通して描いた「田沼主殿頭の身辺」など、博捜した史料から江戸の話題の人物たちの歴史像を鳶魚の独自の目で見直す。「玉川上水の建設者 安松金右衛門」も収録。
*解説頁・朝倉治彦
〈21〉江戸の旧跡 江戸の災害 (えどのきゅうせき えどのさいがい)
(画像はクリックで拡大します)
*409頁
*発行 1998年
*カバー文
久米の平内など浅草・上野の旧跡を回顧した「大江戸の名残り」、永代橋崩落の背後にある人災的側面と政治的背景を深く抉り出した「永代落橋」、火事がもたらした思いがけない風俗の変化を描いた「秋葉ばら」など、江戸の旧跡や地震大火などの災害を考証する。鳶魚の着眼の鋭さと手法の確かさを示す論稿。
*解説 山本博文
〈22〉泥坊の話・お医者様の話 (どろぼうのはなし・おいしゃさまのはなし)
(画像はクリックで拡大します)
*339頁
*発行 1998年
*カバー文
日本左衛門・田舎小僧・葵小僧・鼠小僧など、『江戸の白浪』以降の泥坊たちの史実と、泥坊から江戸という時代を捉えた、鳶魚お得意の泥坊研究六篇と、「御典医の話」「江戸時代の性欲教育」など、医者から見た江戸生活史を描いた九篇を収録する。鳶魚の江戸研究の明確な姿勢を示す一巻。
*解説頁・山本博文
〈23〉江戸の生活と風俗 (えどのせいかつとふうぞく)
〈24〉江戸の豪侠 人さまざま (えどのごうきょう ひとさまざま)
〈25〉お大名の話・武家の婚姻 (おだいみょうのはなし・ぶけのはなし)
〈26〉花柳風俗 (かりゅうふうぞく)
〈27〉元禄快挙別録 (げんろくかいきょべつろく)
〈28〉足の向く儘 (あしのむくまま)
〈29〉芝居風俗 鳶魚江戸文庫 (しばいふうぞく)
(画像はクリックで拡大します)
*336頁 / 発行 1999年
*カバー文
江戸ッ子の悪対・痰火や洒落ッ気について述べた「芝居の産んだ悪対趣味」、女歌舞伎から若衆・野良歌舞伎への変遷を通して、男美女醜論を展開する「人間美の競争」など、江戸庶民の生活に大きな影響をあたえた、芝居・役者の風俗文化を考証する。江戸の風俗の細部に光をあてた17篇。
*解説頁・山本博文
〈30〉江戸生活のうらおもて (えどせいかつのうらおもて)
〈31〉近松の心中物・女の流行 (ちかまつのしんじゅうもの・おんなのりゅうこう)
〈32〉はやり唄・吾妻錦絵 (はやりうた・あづまにしきえ)
〈33〉人形芝居と能 鳶魚江戸文庫 (にんぎょうしばいとのう)
(画像はクリックで拡大します)
*405頁 / 発行 1999年
*カバー文
のろま論の先駆的労作「野呂間人形」考、役者の元結を一種の軍用通信に利用した徳島藩人形遣いの別の一面を描く「淡路の人形座」のほか、関東で唯一の神田明神の神事能や、日本最古の仏教美術の系統を引く壬生狂言等を考察する。日本各地の人形芝居や能など、民間芸能を丹念に渉猟した鳶魚の芸能研究。
*解説頁・山本博文
〈34〉芝・上野と銀座 (しば・うえのとぎんざ)
〈35〉芝居ばなし (しばいばなし)
(画像はクリックで拡大します)
*373頁 / 発行 1999年
*目録文
今では消滅した衣服や調度や髪形など、江戸時代の生活様式を当時の俤を遺している歌舞伎舞台から探る。江戸生活研究の好個の資料。
*解説頁・山本博文
〈36〉江戸雑録 (えどざつろく)
(画像はクリックで拡大します)
*515頁 / 発行 1999年
*カバー文
田沼意次の家来三浦庄二の収賄恐怖譚等を描いた「賄賂と手土産」、近世にさかんだった言葉遊びを扱った「紛失した洒落」、東海道諸川の川留めを具体的に考察した「大井川の川留め」など、江戸時代の諸相を通し江戸生活を探る。これまで等閑視されてきた分野を丹念に考証した、興趣あふれる33篇。
*解説頁・山本博文
別巻〈1〉大衆文芸評判記 (たいしゅうぶんげいひょうばんき)
別巻〈2〉時代小説評判記 (じだいしょうせつひょうばんき)